かつてホールドしていた銘柄を、改めて見直すシリーズ。今回は、「中山福(7442)」を振り返ります。中山福は、家庭用品の販売を行う卸売企業で、20年ほど前の2005年に購入した銘柄。おそらく資産バリュー的な視点で購入した銘柄ですが、わずか3カ月という短い期間保有して、キッチリ損して売っていました。
完全に記憶の片隅に追いやられていた銘柄ですが、20年以上の歳月を経て、ビジネスモデルや株価の推移を改めて見直してみたいと思います。
中山福のビジネスモデル

中山福は、1925年に中山福松氏が大阪で創業し、1947年に法人化。家庭金物の卸売業を基盤に成長し、1963年に現在の社名へ変更。正式な社名表記は『中山福株式会社』で旧字の「福」ですが、一般的な表記としては『中山福』も使用されています。全国展開を進め、1995年に大阪証券取引所二部へ上場し、2003年には一部へ指定替え。2006年に東証二部に上場し、2008年に一部へ指定替えとなりました。
主に家庭用品の卸売業で、ホームセンターやスーパー向けに調理用品、収納用品などを販売。特にホームセンター業界での販売力が高く、安定した売上基盤を確保しています。さらに、EC市場拡大に向けた戦略として、EC専業子会社を活用し、BtoC向けオンライン販売にも進出しています。
中山福の業績

| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 444.9 | 2.1 | 1.4 |
| 2016年 | 485.1 | 2.2 | 1.4 |
| 2017年 | 479.8 | 1.3 | 0.9 |
| 2018年 | 473.9 | 0.9 | 0.5 |
| 2019年 | 484.9 | 0.9 | 0.4 |
| 2020年 | 466.6 | 0.5 | 0.2 |
| 2021年 | 478.7 | 1.3 | 1.0 |
| 2022年 | 427.2 | 0.9 | 0.6 |
| 2023年 | 398.9 | 0.5 | 0.6 |
| 2024年 | 385.9 | -0.1 | 0.1 |
中山福の近年の事業環境は、厳しさを増しています。業界全体として、主要な販売市場での競争激化、資源価格の高騰、円安の影響による仕入価格や物流費の上昇が続いています。また、消費者の節約志向の高まりから、家庭用品の需要は伸び悩んでいます。国内消費市場は停滞がつづいており、物価上昇が家計負担を増やしているため、消費者の購買意欲が減少しているのが現状。
2021年まで比較的売上は安定し、特にコロナ禍においては巣ごもり需要が追い風となったようです。ただコロナ禍が落ち着くとその反動で、売上は減少傾向にあります。2024年3月期の売上高は約385億円で、目標の410億円には届かず、経常損失は約1.3億円となりました。前年と比較しても売上は減少しており、利益面でも厳しい状況が続いています。近年は大手ECサイトやメーカー直販の増加により、従来の卸売業の役割が変化してきています。
そうした危機感から中山福もECサイトを立ち上げていますが、大手ECプラットフォームとの競争や物流コストの増加といった課題が残っています。実際に店舗で商品を手に取り品質を確認してから購入する層も一定数存在する一方、Amazonや楽天でのリサーチを行う消費者は今後も増えていくでしょう。そういう点で中山福の環境は、厳しさが続くように思えます。
中山福の株価


アベノミクスで50%ほど上げたものの、そこからはひたすら下がり続け一時期ピークの1/3まで落ち込んでいます。コロナ禍で業績が良かった割には瞬間的な上げで終わったようです。上場時からの長期保有では、最大で+50%程度のリターンが見込めたものの、現在の株価は当時と比べて低迷しており、長期投資の観点からは厳しい状況といえます。
PERは10倍程度と市場平均と比較して割安に見えますが、事業の成長余地が限られている点を考慮すると、適正水準と見ることもできます。ただ自己資本比率も70%近くあり、財務も良好なので資産的な割安さでいえば、PBR0.3倍と激安です。配当利回りが2.7%ほどなので、資産バリューとして持つにはここが弱いところかもしれません。
まとめ

基本的に卸売業が逆風でしかないので、事業環境において買いたいと思うセクターではありません。資産バリューとしての魅力はあるものの、成長性に乏しく、長期的なリターンを期待するのは難しいかもしれません。ちなみに中山福松さんが創業して「中山福松商店」でスターとしていますが、社名変更後は「松」だけを取った「中山福」にしています。なぜ福だけのこしたのか、謎は深まるばかりです。






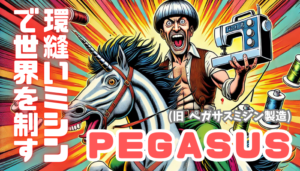

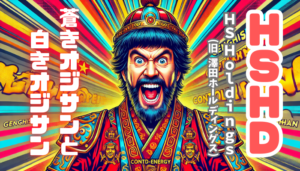
コメント